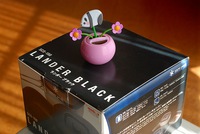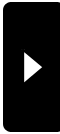2008年01月26日
えあぶらについて
先日,PINGUさんにコメント頂いて答えられなかった,「えあぶら」について,ちょっと勉強してみました。

今日は,家具などに使う塗料のうち 天然系オイル全般について,浅~い知識を披露させていただきます。
ですので,内容についてのご質問には,知識が追いつかないのでお答えできないことをあらかじめお断りしておきます。
さて,僕がランタンケースに行った荏油の塗布は,オイルフィニッシュという塗布方法のようです。
オイルフィニッシュとは、空気中の酸素を吸って固まる性質のある油、乾性油を木にしみこませる方法そうです。
先日のADIAさんの記事にあった,クーラーボックススタンドの天板にチークオイルを塗られていたのも同じような方法です。
http://bousai.naturum.ne.jp/d2007-10.html
「油が酸化する」と言いますが、油の分子と酸素がくっつく二重結合というのがあります。
この二重結合をどれだけ持っているかが油の性質を知る上で重要で、そのため、この部分に酸素のかわりにヨー素をひっつけて結合するヨー素の量から、二重結合の多さ、言いかえれば酸素のひっつきやすさを測定する。これがヨー素価です。
ヨー素価が大きいと酸化しやすく、重合して樹脂化しやすいことになります。
このヨー素価をもとに以下のように乾燥しやすい乾性油、ほとんど樹脂化しない不乾性油、中間の半乾性油の三つに分類されます。
こんな感じの文章が続きますが,・・・。

今日は,家具などに使う塗料のうち 天然系オイル全般について,浅~い知識を披露させていただきます。
ですので,内容についてのご質問には,知識が追いつかないのでお答えできないことをあらかじめお断りしておきます。
さて,僕がランタンケースに行った荏油の塗布は,オイルフィニッシュという塗布方法のようです。
オイルフィニッシュとは、空気中の酸素を吸って固まる性質のある油、乾性油を木にしみこませる方法そうです。
先日のADIAさんの記事にあった,クーラーボックススタンドの天板にチークオイルを塗られていたのも同じような方法です。
http://bousai.naturum.ne.jp/d2007-10.html
「油が酸化する」と言いますが、油の分子と酸素がくっつく二重結合というのがあります。
この二重結合をどれだけ持っているかが油の性質を知る上で重要で、そのため、この部分に酸素のかわりにヨー素をひっつけて結合するヨー素の量から、二重結合の多さ、言いかえれば酸素のひっつきやすさを測定する。これがヨー素価です。
ヨー素価が大きいと酸化しやすく、重合して樹脂化しやすいことになります。
このヨー素価をもとに以下のように乾燥しやすい乾性油、ほとんど樹脂化しない不乾性油、中間の半乾性油の三つに分類されます。
こんな感じの文章が続きますが,・・・。
乾性油:ヨー素価130以上(主用途=塗料) 亜麻仁油(130)、桐油(160)、荏油(200)、クルミ油(150)
木に浸透し、樹脂化することで木の補強、防水、対汚染性、美化をねらう
亜麻仁油:乾性油でもっともよく使われる。乾燥がおそい。黄変する。
煮亜麻仁油:重合度を高めただけではなく、金属酸化物の乾燥剤を含む。
桐油:亜麻仁油よりもやや防水性がある。黄変も少ない。
荏油:乾燥しやすく、多少ニスのような光沢がある。焼け色がはげしい。
半乾性油:ヨー素価100~130(主用途=食用油) ゴマ油(110)、ワタ油(106)、ナタネ油(100)、ダイズ油
乾性油に準じた目的で使用
胡麻油:温度をあげて塗布しないとべたつく。
菜種油: 同上 、サラダオイルでも同じ。
不乾性油:ヨー素価100以下(主用途=毛髪用等) ツバキ油(31)、オリーブ油、ヒマシ油、ヤシ油
硬化しない油
オリーブ油:湿った感じで無塗装に近いが、数年たつといいあめ色に。
椿油:あまり経験はないが、無塗装に近い感じ。
1.塗布用オイルの分類
さらに,塗布用に使われるオイルは,乾性油・天然蝋・柿渋などに区分されています。
1)乾性油
分子中に、空気中の酸素が化合する二重結合を持っている油で、この反応によって樹脂化する。
完全に固くはならないので、木の収縮によってひび割れなどは生じにくい。
この重合反応で熱が発生するので、使ったボロ布などを捨てる時は、熱がこもって自然発火しないように注意する必要がある。
焼却処分、水中保存、一枚ずつ広げて充分乾燥後捨てるなどの方法をとる。
亜麻仁油や荏油がこれに属するようです。
2)天然蝋
蝋は,人間とのつきあいの長い油脂ですね。
西洋では蜜蝋、日本では木蝋の歴史が長い。植物蝋、動物蝋に分類されます。
融点の高い低いによっても用途が変わってくることが多い。
昔、ろうそくは貴重な明かり源であり、庶民は油を灯芯でもやし、寺社などでの儀式で高価な和蝋燭が用いられたようだ。
蜜蝋は蜂蜜を採取する時に上にういてくる口紅などの化粧品にも使われる黄色い動物蝋。
木蝋は日本、特に福岡、愛媛、大分などの特産品。未漂白のものは緑色で生蝋と言い、漂白したものは白蝋と呼ぶ。
このほか,カルナバ蝋やイボタ蝋などがある。
3)その他
柿渋は,渋柿の成分を熟成させて作られるものである。中風の薬として飲用されたり、日本酒の醸造過程で使われる柿渋は、古くから、和紙や網の防水防腐剤として使われています。渋柿の汁を醗酵させて作る柿渋や京都山城地方の特産品。木に塗ってもすぐには発色しないが、数日経つと赤みがかった茶色になる。乾燥後は匂いがしないが、乾かないうちは独特の生臭い匂いがある。安全で手軽にぬれる日本独特の塗料である。
食用の他、電気のなかった昔、夜のあかりに東西を問わず用いられた。西洋ではオリーブ油、コルザ油、シード・オイル、熱帯地方ではヤシ油、クワイ油、ヒマシ油、アマニ油などが、日本では大宝令に地方からの貢献を義務づけた油として、ゴマ油、アサ油、荏油などが記録に残っています。乾性油は防水や補強剤として雨傘、合羽、油紙にも用いられた。この方面での利用が現在のオイルフィニッシュの用法に近いと思われます。
2.オイルフィニッシュの方法
1)充分に塗布し、浸透させる。
20~30分後、過剰な油をしっかり拭き取る。
(20~30分の時間は油が導管中の空気と入れ替わるのに必要な時間)
充分に乾燥させる。
古いTシャツなどの毛羽立ちのないボロ布やスポンジで塗る。
小物は油に漬け込んでもよい(ドブヅケ)。
浸透性をよくするため、亜麻仁油は小さな泡ができるぐらいに加熱して塗る。
加熱する代わりに、溶剤で粘度を下げる。(溶剤蒸気に注意。テレピン油、ペイントうすめ液等)
できれば加熱塗布がいいようです。溶剤蒸気の危険性がなく、また油が薄くならないからです。
2)拭き取り 拭き取ったところがわかりにくいので、順序を決めるなどしてもれなく拭き取る。
布がボトボトになったら取り替える。
導管から油が噴き出して来る場合はその後も拭き取りを続行。
濡れた状態で研磨をする方法もあります。この方法は木のカスと乾性油のミックスを導管につめてシーラーのようにしてしまうので、この方法で仕上げるとツルツルにはなりますが、表面が樹脂っぽくなり、クリアラッカー仕上げに近くなるように感じます。
通常は1回目のオイルがよく乾いてから400番~600番で再研磨し、よくホコリをとってから2回目の塗布をします。塗布回数は4回ぐらいで、最後にワックスで磨くと光沢がすばらしくなります。しかし使い込んで仕上げていく考え方では、1回~2回でよいかもしれません(特に鉋仕上げの針葉樹の場合)。
3)着色したいとき
あまり濃い着色は無理ですが、オイルステインを少量油に混ぜればOK。本来は油性染料を混入すべきですが、少量の入手は困難ですし、完全な撹拌がむつかしそうです。
3.柿渋の塗布方法
柿渋の塗り方の基本は、薄めに塗っては乾かすを繰り返すことです。また、原液のまま漬けるように塗るのも面白く、漆にも似た光沢が得られます。塗った直後はほとんど着色しませんが、天日にあてて乾燥させると、数日で独特の色合いになります。
乾燥するまでは、独特な生臭い匂いがありますが、乾燥後は匂わなくなります。また柿渋は中風の薬としても飲用されるくらいで、人体に害はありません。
塗った時の毛羽立ちが少ないので、鉋で仕上げる方が望ましい。研磨紙使用の場合は細目を用い、カスなどがのこらないようによく拭き取ること。
水で約2倍に薄めた柿渋を刷毛で塗り過剰分を布で拭き取り乾燥させる。
乾燥すると木地が毛羽立つので、400番ぐらいの研磨紙をかるくかけるなどして、表面を平滑にする。
刷毛や容器は水でよく洗って下さい。
タンニンが主成分なので、鉄分があると黒くなります。塗る前に研磨紙のカスなどが残らないように注意して下さい。
木に浸透し、樹脂化することで木の補強、防水、対汚染性、美化をねらう
亜麻仁油:乾性油でもっともよく使われる。乾燥がおそい。黄変する。
煮亜麻仁油:重合度を高めただけではなく、金属酸化物の乾燥剤を含む。
桐油:亜麻仁油よりもやや防水性がある。黄変も少ない。
荏油:乾燥しやすく、多少ニスのような光沢がある。焼け色がはげしい。
半乾性油:ヨー素価100~130(主用途=食用油) ゴマ油(110)、ワタ油(106)、ナタネ油(100)、ダイズ油
乾性油に準じた目的で使用
胡麻油:温度をあげて塗布しないとべたつく。
菜種油: 同上 、サラダオイルでも同じ。
不乾性油:ヨー素価100以下(主用途=毛髪用等) ツバキ油(31)、オリーブ油、ヒマシ油、ヤシ油
硬化しない油
オリーブ油:湿った感じで無塗装に近いが、数年たつといいあめ色に。
椿油:あまり経験はないが、無塗装に近い感じ。
1.塗布用オイルの分類
さらに,塗布用に使われるオイルは,乾性油・天然蝋・柿渋などに区分されています。
1)乾性油
分子中に、空気中の酸素が化合する二重結合を持っている油で、この反応によって樹脂化する。
完全に固くはならないので、木の収縮によってひび割れなどは生じにくい。
この重合反応で熱が発生するので、使ったボロ布などを捨てる時は、熱がこもって自然発火しないように注意する必要がある。
焼却処分、水中保存、一枚ずつ広げて充分乾燥後捨てるなどの方法をとる。
亜麻仁油や荏油がこれに属するようです。
2)天然蝋
蝋は,人間とのつきあいの長い油脂ですね。
西洋では蜜蝋、日本では木蝋の歴史が長い。植物蝋、動物蝋に分類されます。
融点の高い低いによっても用途が変わってくることが多い。
昔、ろうそくは貴重な明かり源であり、庶民は油を灯芯でもやし、寺社などでの儀式で高価な和蝋燭が用いられたようだ。
蜜蝋は蜂蜜を採取する時に上にういてくる口紅などの化粧品にも使われる黄色い動物蝋。
木蝋は日本、特に福岡、愛媛、大分などの特産品。未漂白のものは緑色で生蝋と言い、漂白したものは白蝋と呼ぶ。
このほか,カルナバ蝋やイボタ蝋などがある。
3)その他
柿渋は,渋柿の成分を熟成させて作られるものである。中風の薬として飲用されたり、日本酒の醸造過程で使われる柿渋は、古くから、和紙や網の防水防腐剤として使われています。渋柿の汁を醗酵させて作る柿渋や京都山城地方の特産品。木に塗ってもすぐには発色しないが、数日経つと赤みがかった茶色になる。乾燥後は匂いがしないが、乾かないうちは独特の生臭い匂いがある。安全で手軽にぬれる日本独特の塗料である。
食用の他、電気のなかった昔、夜のあかりに東西を問わず用いられた。西洋ではオリーブ油、コルザ油、シード・オイル、熱帯地方ではヤシ油、クワイ油、ヒマシ油、アマニ油などが、日本では大宝令に地方からの貢献を義務づけた油として、ゴマ油、アサ油、荏油などが記録に残っています。乾性油は防水や補強剤として雨傘、合羽、油紙にも用いられた。この方面での利用が現在のオイルフィニッシュの用法に近いと思われます。
2.オイルフィニッシュの方法
1)充分に塗布し、浸透させる。
20~30分後、過剰な油をしっかり拭き取る。
(20~30分の時間は油が導管中の空気と入れ替わるのに必要な時間)
充分に乾燥させる。
古いTシャツなどの毛羽立ちのないボロ布やスポンジで塗る。
小物は油に漬け込んでもよい(ドブヅケ)。
浸透性をよくするため、亜麻仁油は小さな泡ができるぐらいに加熱して塗る。
加熱する代わりに、溶剤で粘度を下げる。(溶剤蒸気に注意。テレピン油、ペイントうすめ液等)
できれば加熱塗布がいいようです。溶剤蒸気の危険性がなく、また油が薄くならないからです。
2)拭き取り 拭き取ったところがわかりにくいので、順序を決めるなどしてもれなく拭き取る。
布がボトボトになったら取り替える。
導管から油が噴き出して来る場合はその後も拭き取りを続行。
濡れた状態で研磨をする方法もあります。この方法は木のカスと乾性油のミックスを導管につめてシーラーのようにしてしまうので、この方法で仕上げるとツルツルにはなりますが、表面が樹脂っぽくなり、クリアラッカー仕上げに近くなるように感じます。
通常は1回目のオイルがよく乾いてから400番~600番で再研磨し、よくホコリをとってから2回目の塗布をします。塗布回数は4回ぐらいで、最後にワックスで磨くと光沢がすばらしくなります。しかし使い込んで仕上げていく考え方では、1回~2回でよいかもしれません(特に鉋仕上げの針葉樹の場合)。
3)着色したいとき
あまり濃い着色は無理ですが、オイルステインを少量油に混ぜればOK。本来は油性染料を混入すべきですが、少量の入手は困難ですし、完全な撹拌がむつかしそうです。
3.柿渋の塗布方法
柿渋の塗り方の基本は、薄めに塗っては乾かすを繰り返すことです。また、原液のまま漬けるように塗るのも面白く、漆にも似た光沢が得られます。塗った直後はほとんど着色しませんが、天日にあてて乾燥させると、数日で独特の色合いになります。
乾燥するまでは、独特な生臭い匂いがありますが、乾燥後は匂わなくなります。また柿渋は中風の薬としても飲用されるくらいで、人体に害はありません。
塗った時の毛羽立ちが少ないので、鉋で仕上げる方が望ましい。研磨紙使用の場合は細目を用い、カスなどがのこらないようによく拭き取ること。
水で約2倍に薄めた柿渋を刷毛で塗り過剰分を布で拭き取り乾燥させる。
乾燥すると木地が毛羽立つので、400番ぐらいの研磨紙をかるくかけるなどして、表面を平滑にする。
刷毛や容器は水でよく洗って下さい。
タンニンが主成分なので、鉄分があると黒くなります。塗る前に研磨紙のカスなどが残らないように注意して下さい。
Posted by 掘 耕作 at 03:32
│自作工夫
★コメントありがとうございます
お早う御座います(^ー^* )
いやー実にマニアックなお話ですね~♪
多分、この手のテストが有るから暗記してこーい!!!
と言われても、もはや頭がついていかなそうです(^_^;)
堀さんやPINGUさんみたいに好きな人だったら
自然に頭に入っていくんだろうなぁ~ヾ(´ー` )ノ
いやー実にマニアックなお話ですね~♪
多分、この手のテストが有るから暗記してこーい!!!
と言われても、もはや頭がついていかなそうです(^_^;)
堀さんやPINGUさんみたいに好きな人だったら
自然に頭に入っていくんだろうなぁ~ヾ(´ー` )ノ
Posted by lilt at 2008年01月26日 09:22
おはようございます。
紹介ありがとございます。
何となくは知っていても、きちんとした知識はないのでいい勉強になりました。
私は柿渋好きなんですよね。
塗ってから色が濃くなるところが好きなんですが、キャンプで使う直前の使用は匂いが消えないので、早めに使う必要がありますね。
鉈、和ナイフの持ち手に使ったときは、鉄に接触するので、塗る前にくぎを入れて黒く変色させてから使ってみました。
塗料としていいか悪いかは判りませんが、黒っぽく渋くなりますよ。
紹介ありがとございます。
何となくは知っていても、きちんとした知識はないのでいい勉強になりました。
私は柿渋好きなんですよね。
塗ってから色が濃くなるところが好きなんですが、キャンプで使う直前の使用は匂いが消えないので、早めに使う必要がありますね。
鉈、和ナイフの持ち手に使ったときは、鉄に接触するので、塗る前にくぎを入れて黒く変色させてから使ってみました。
塗料としていいか悪いかは判りませんが、黒っぽく渋くなりますよ。
Posted by ADIA at 2008年01月26日 09:44
これまた難しい話ですな(笑)
とゆか、読めない漢字すらございますが(笑)
でも、作業は楽しそう!
とゆか、読めない漢字すらございますが(笑)
でも、作業は楽しそう!
Posted by parrPEAME at 2008年01月26日 09:52
いや~難しいはなしには頭がついていかないところもあるのですが・・・(^^;)
柿渋は、義父が昔、反物の職人をしていて、絵柄の型おこしの時に使っていたと聞いたことがあります。
型を何回も液に浸して使うための強度のためとか・・・
記憶があってればですが(^^)
先人の知恵のような品で、味があるものいいですよね~
木の無垢だと傷みやすいし、長く使えるようにしたいですものね。
柿渋は、義父が昔、反物の職人をしていて、絵柄の型おこしの時に使っていたと聞いたことがあります。
型を何回も液に浸して使うための強度のためとか・・・
記憶があってればですが(^^)
先人の知恵のような品で、味があるものいいですよね~
木の無垢だと傷みやすいし、長く使えるようにしたいですものね。
Posted by marurin at 2008年01月26日 10:02
at 2008年01月26日 10:02
 at 2008年01月26日 10:02
at 2008年01月26日 10:02★liltさん
こんにちは
こんな難しいこと,頭になんか入りませんよ!!(笑)
あちこち調べてみただけです。
でも,木質に適当な油を塗っておけば長持ちするって感じは理解していただけたでしょ!
こんにちは
こんな難しいこと,頭になんか入りませんよ!!(笑)
あちこち調べてみただけです。
でも,木質に適当な油を塗っておけば長持ちするって感じは理解していただけたでしょ!
Posted by 掘 耕作 at 2008年01月26日 12:53
at 2008年01月26日 12:53
 at 2008年01月26日 12:53
at 2008年01月26日 12:53★ADIAさん
こんにちは
勝手にトラックバックとリンクさせていただきました。
今回は,適当に材料を選んで塗ってみましたが,臭いが抜けなくて,少々困っています。
奥さんからのクレームが大変です。
柿渋に塗りなおしたい~って感じです。
こんにちは
勝手にトラックバックとリンクさせていただきました。
今回は,適当に材料を選んで塗ってみましたが,臭いが抜けなくて,少々困っています。
奥さんからのクレームが大変です。
柿渋に塗りなおしたい~って感じです。
Posted by 掘 耕作 at 2008年01月26日 12:56
at 2008年01月26日 12:56
 at 2008年01月26日 12:56
at 2008年01月26日 12:56★parrPEAMEさん
こんにちは
難しいってことは,読んでいただいたと言うことですね。
僕だったら,読まずに逃げますが・・・。
コメントありがとうございます。
こんにちは
難しいってことは,読んでいただいたと言うことですね。
僕だったら,読まずに逃げますが・・・。
コメントありがとうございます。
Posted by 掘 耕作 at 2008年01月26日 12:57
at 2008年01月26日 12:57
 at 2008年01月26日 12:57
at 2008年01月26日 12:57★marurinさん
こんにちは
柿渋を塗って,和紙を補強するのは,伊勢型紙などでも使われる技法ですね。
義父さんが,職人だったと。
それは,貴重なことですよ。
ぜひ,柿渋を使ってキャンプ用品を染めてみてください(笑)
シャンティーとか(失礼)
こんにちは
柿渋を塗って,和紙を補強するのは,伊勢型紙などでも使われる技法ですね。
義父さんが,職人だったと。
それは,貴重なことですよ。
ぜひ,柿渋を使ってキャンプ用品を染めてみてください(笑)
シャンティーとか(失礼)
Posted by 掘 耕作 at 2008年01月26日 13:01
at 2008年01月26日 13:01
 at 2008年01月26日 13:01
at 2008年01月26日 13:01詳細な記事ありがとうございます(^O^)
荏油は和室の飾り物とかに合いそうですね
ケヤキ飾り物とかに使うと 実に渋い光沢との事
色々あるもんですねー
我が家はごく普通のラッカー系ニスとオイルステインで仕上げちゃってますが
柿渋でのフィニッシュ 今度やってみますよ!
って コレが似合うキャンプ道具ってなんだろー??
ランタンケースも 入れる物がペトロマックスならいいけど
ごく普通のコールマンランタンじゃなんとも(笑)
またよろしくお願いします!
荏油は和室の飾り物とかに合いそうですね
ケヤキ飾り物とかに使うと 実に渋い光沢との事
色々あるもんですねー
我が家はごく普通のラッカー系ニスとオイルステインで仕上げちゃってますが
柿渋でのフィニッシュ 今度やってみますよ!
って コレが似合うキャンプ道具ってなんだろー??
ランタンケースも 入れる物がペトロマックスならいいけど
ごく普通のコールマンランタンじゃなんとも(笑)
またよろしくお願いします!
Posted by PINGU at 2008年01月26日 19:49
at 2008年01月26日 19:49
 at 2008年01月26日 19:49
at 2008年01月26日 19:49☆PINGUさん
こんばんは
自分でもよく分からずに書いている部分が多々あります。
ケヤキに赤っぽい色は似合いそうですね。
ぼくも,柿渋はちゃんと使ったことがないんですよ。
焚き火テーブルで使い損ないました。
コールマンも十分渋さを演出出来ると思います。
色々楽しいので,また課題を下さいね。
記事を作るのにちょっと難儀してます。
こんばんは
自分でもよく分からずに書いている部分が多々あります。
ケヤキに赤っぽい色は似合いそうですね。
ぼくも,柿渋はちゃんと使ったことがないんですよ。
焚き火テーブルで使い損ないました。
コールマンも十分渋さを演出出来ると思います。
色々楽しいので,また課題を下さいね。
記事を作るのにちょっと難儀してます。
Posted by 掘 耕作 at 2008年01月26日 20:31
at 2008年01月26日 20:31
 at 2008年01月26日 20:31
at 2008年01月26日 20:31素晴らしい知識ですね(^^)v。
半分以上判りません、、、、、(^^;)。が、何やら凄いことだけは判りました。
堀さん、凄い!。
半分以上判りません、、、、、(^^;)。が、何やら凄いことだけは判りました。
堀さん、凄い!。
Posted by ライダー at 2008年01月26日 22:54
at 2008年01月26日 22:54
 at 2008年01月26日 22:54
at 2008年01月26日 22:54ほーほー、こんな物があるんですねぇ!
初めて知りましたよ(^^
きっと昔からこういう物ってあるんでしょうね。
これの究極が漆ですかね?
そう言えば胡桃の実で手作りの木工製品に味を出すのとか
やった事あります。
手っ取り早くいい感じになるので重宝したのを思い出しました~~
初めて知りましたよ(^^
きっと昔からこういう物ってあるんでしょうね。
これの究極が漆ですかね?
そう言えば胡桃の実で手作りの木工製品に味を出すのとか
やった事あります。
手っ取り早くいい感じになるので重宝したのを思い出しました~~
Posted by lag at 2008年01月26日 23:15
at 2008年01月26日 23:15
 at 2008年01月26日 23:15
at 2008年01月26日 23:15☆ライダーさん
おはようございます
僕も書いていて,半分以上分かっていません(笑)
ということで,全然凄くないです。
おはようございます
僕も書いていて,半分以上分かっていません(笑)
ということで,全然凄くないです。
Posted by 掘 耕作 at 2008年01月27日 06:41
at 2008年01月27日 06:41
 at 2008年01月27日 06:41
at 2008年01月27日 06:41☆lagさん
漆ですか。
かなり,マニアックなものだと思いますが,扱いにくさはどの程度でしょう。
入手経路も分かりませんよ。
でも,春慶塗り風の仕上がりが出来たらかっこよさそうですね。
テーブルとか,ランタンケースとか,
かなりかっこよさそうです。
クルミの実をすりつけるのかな?
油を取って使ったんかな?
漆ですか。
かなり,マニアックなものだと思いますが,扱いにくさはどの程度でしょう。
入手経路も分かりませんよ。
でも,春慶塗り風の仕上がりが出来たらかっこよさそうですね。
テーブルとか,ランタンケースとか,
かなりかっこよさそうです。
クルミの実をすりつけるのかな?
油を取って使ったんかな?
Posted by 掘 耕作 at 2008年01月27日 06:47
at 2008年01月27日 06:47
 at 2008年01月27日 06:47
at 2008年01月27日 06:47はずかしい話・・・えあ油っていうんですねぇ
小さいころから祖父(もうず~と前に他界しましたが)が、
縁側とかに塗っているのをうる覚えで記憶があるんですが・・・
そのころから「えな油」と言っていたと覚えていたようです。
あれから30数年・・・・・間違えに気がつきました (笑
小さいころから祖父(もうず~と前に他界しましたが)が、
縁側とかに塗っているのをうる覚えで記憶があるんですが・・・
そのころから「えな油」と言っていたと覚えていたようです。
あれから30数年・・・・・間違えに気がつきました (笑
Posted by dacyan at 2008年01月27日 10:09
☆だっちゃん
こんにちは
えあ油って入力ミスですよね。
「えあぶら」です。
エゴマの油が原料ということだそうですよ。
しかし,良く覚えてましたね。
こんにちは
えあ油って入力ミスですよね。
「えあぶら」です。
エゴマの油が原料ということだそうですよ。
しかし,良く覚えてましたね。
Posted by 掘 耕作 at 2008年01月27日 12:29
at 2008年01月27日 12:29
 at 2008年01月27日 12:29
at 2008年01月27日 12:29